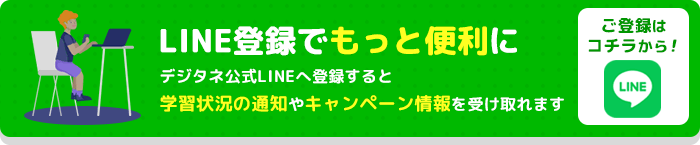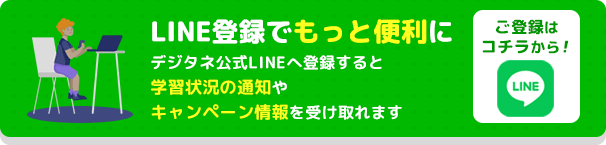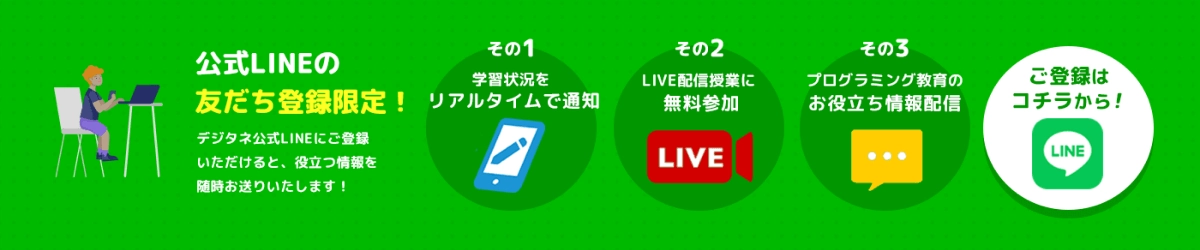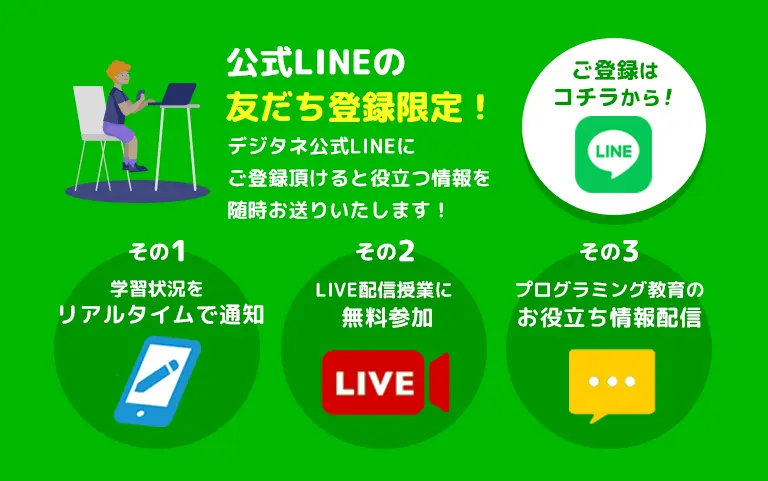「マイクラって、ほんとに教育にいいの?」
おそらくこの記事にたどり着いた方の多くが、そんな疑問を感じているのではないでしょうか。
「うちの子が夢中になってるけど、ただのゲームじゃないの?」
「学びになるって聞くけど、実際どんな力がつくの?」
そんな声、保護者の方からよく耳にします。
でも実は、マインクラフト(通称マイクラ)はいま、世界中の教育現場でも使われ始めている“学びの道具”なんです。
もちろん、何も考えずにただ遊んでいるだけでは学びにはなりません。でも、「使い方」次第で、子どもの思考力や創造力、さらには自信や人間関係の力まで、いろんな力が育っていきます。
この記事では、マイクラがなぜ「教育に良い」と言われているのかを、現場の視点と実例を交えながら、できるだけわかりやすく、かつ具体的にご紹介していきます。
子どもがゲームに夢中になる姿に不安を感じていた方も、「こんな力が育つんだ」と新たな発見があるかもしれません。

マイクラで学べる!小中学生向けオンラインプログラミング教材「デジタネ」。
ただマイクラで遊んでいる時間を、マイクラで遊びつつ「将来のためになる時間」に変えませんか?
まずは無料体験で、お子さまにピッタリかどうか試してみましょう!
- 1. マインクラフトはどんなゲーム?
- 2. マインクラフトが教育に注目される理由とは
- 3. 教育に役立つ理由を具体的に!マイクラで育つ5つの力
- ・①「こんなもの作ってみたい!」という気持ちが、子どもの「創造力」を伸ばしていく
- ・②気づけば“考えるクセ”がついている。遊びの中で育つ「論理的思考」と「問題解決能力」
- ・③「どうやったらできるかな?」正解のない世界だから育つ「主体性」と「探究心」
- ・④一緒に遊ぶ中で自然と身につく「伝える力」と「協力する力」
- ・⑤「できた!」が自信になる。マイクラが育てる「自己肯定感」
- 4. マイクラを“学びの時間”にするコツ
- ・親子で一緒にプレイする
- ・「今日はここまで」を決める。それだけで遊びが学びに変わる
- ・「それ、マイクラでやってみたら?」って言いたくなる活用アイデア
- 5. マイクラで広がる、プログラミングの世界
- ・遊びながら“コードのしくみ”が体感できる
- ・マイクラを活用したビジュアルプログラミング教材「マイクラッチ」
- 6. まとめ|「遊び」が「学び」に変わる瞬間を、一緒に見届けてみませんか?
マインクラフトはどんなゲーム?
「マイクラ」と呼ばれて親しまれているマインクラフトは、四角いブロックでできた広大な世界を自由に冒険できるゲームです。
家を建てたり、村を作ったり、洞窟を探検したり、空に浮かぶ島を作ったり…やりたいことはプレイヤー次第。はっきりした“クリア”や“ストーリー”があるわけではなく、自分で目的を決めて進めていくスタイルが特徴です。
ちょっと乱暴に言えば、「レゴを仮想空間に持ち込んで、しかも一緒に遊べる友だちが世界中にいる」という感じかもしれません。
遊び方にもいろいろあり、「サバイバルモード」ではモンスターに襲われないように生活しながら資源を集めたり、「クリエイティブモード」では材料や制限を気にせず自由に建築を楽しんだりできます。
さらに、パソコン・スマホ・ゲーム機などいろんな端末で遊べて、友達と一緒にプレイすることもできるので、飽きずに続けられる子も多いです。
とはいえ、大人から見ると「結局ゲームでしょ?」と思う気持ちもよくわかります。
でも実際には、この自由すぎるゲーム性こそが、子どもの“考える力”や“創造する力”を刺激してくれる要素になっているんです。
マインクラフトが教育に注目される理由とは
最近では「マイクラを授業で使っています」という学校も少しずつ増えてきました。
一昔前なら「ゲームを授業に?」と驚かれたかもしれませんが、いまやマインクラフトは世界中の教育現場で、“遊びながら学ぶ”ための教材として活用されています。
その背景にあるのは、マイクラの持つ“自由さ”と“奥深さ”です。
マイクラには「こうしなさい」「次はこれをしてね」といった決まった進行はありません。だからこそ、子どもたちは自分で目的を見つけ、どうやって達成するかを考える力が自然と鍛えられていきます。
たとえば、「かっこいいお城を作ってみたい!」と思ったとき、
必要な素材を集めて、どう組み立てれば崩れないかを考えて、時には壊してやり直して…そんな試行錯誤の繰り返しが、創造力・論理的思考・計画性など、まさに学びの基礎につながっていくんです。
さらに、世界中の教育機関が注目している理由のひとつが「教育版マインクラフト(Minecraft Education)」の存在です。
これは学校や学習塾向けに開発された特別なバージョンで、実際の授業で使えるようにテーマ別のワールド(世界)や教材が組み込まれています。
たとえば、歴史の授業で古代都市を再現したり、理科の授業で食物連鎖を体験したりといった使い方もあります。
もちろん、家庭用の通常バージョンでも教育的な効果は十分に期待できます。
「難しい操作ができないと意味がない」ということもなく、子どもが自然な流れで夢中になれるのがマイクラの強みです。
教育に役立つ理由を具体的に!マイクラで育つ5つの力
ここまで読んで、「なんとなく良さそうなのはわかったけど、具体的にどんな力が身につくの?」と思われたかもしれません。
実はマインクラフトは、ただ楽しいだけのゲームではありません。
子どもが夢中になって遊んでいるその時間の中には、考える力・伝える力・工夫する力など、将来につながるたくさんの“学びの種”が詰まっています。
このセクションでは、教育の現場でも注目されている「マイクラで育つ5つの力」を、できるだけわかりやすく、日常に近い視点で紹介していきます。
お子さんの「ゲームにハマっている姿」が、もしかすると大きな成長の兆しかもしれません。
①「こんなもの作ってみたい!」という気持ちが、子どもの「創造力」を伸ばしていく
マイクラの最大の魅力は、「何をしてもいい」という圧倒的な自由さにあります。誰かに指示されるのではなく、自分の中にある“やってみたい”という気持ちがすべてのスタート。
最初はただブロックを積み重ねているだけだった子が、いつの間にか「秘密基地を作ってみたい」「学校みたいな建物を再現してみたい」と、自分なりのアイデアを形にし始めます。
この「つくってみたい」という気持ちこそ、まさに創造力の原点。
ブロックをどう並べたらうまくいくか、見た目はどう工夫するか、素材は何が合っているか…。試行錯誤を重ねながら、自分の頭の中にあるイメージを少しずつ“かたち”にしていく過程は、立派な思考活動であり、創造のトレーニングそのものです。
しかも、失敗してもすぐにやり直せるのがマイクラの良いところ。
「もう一回試してみよう」「今度はこうやってみよう」と前向きに挑戦し続ける姿は、まるでデジタルの工作や絵画のような学びにも見えます。
大人が思っている以上に、子どもたちは「何をつくるか」「どう表現するか」を頭の中で練っています。
その姿を見て、「ただ遊んでるだけ」ではなく、想像力をフル回転させているんだなと感じていただけると思います。
②気づけば“考えるクセ”がついている。遊びの中で育つ「論理的思考」と「問題解決能力」
マインクラフトの世界では、「なんとなく」でうまくいくことは意外と少ないんです。
たとえば家を建てるにも、形や広さを決めて、必要な材料を揃えて、どんな順番で作業するかを考える必要があります。
ちょっとずつズレてしまったり、材料が足りなくなったりすれば、やり直しも必要になる。こうした“計画→実行→修正”の流れを、子どもたちは自然と何度も繰り返しています。
また、マイクラには「レッドストーン」という素材を使った回路システムもあります。これは電気のスイッチのようなもので、仕組みを理解するとドアの自動開閉や装置の連動などができるようになるんですが、最初はうまく動かないことのほうが多いんです。
「どうして動かないんだろう」
「どこかにミスがあるのかな」
「順番が間違ってるかも」
こうやって少しずつ原因を探していくプロセスこそ、まさに論理的思考そのもの。
大人が教えなくても、子どもたちは“うまくいかせたい”という気持ちから、自然に“考えるクセ”を身につけていきます。
しかも、それが「面白い」「もっとやってみたい」という感情と結びついているからこそ、思考力がしっかり定着していきます。
マイクラには、そんな「思考の筋トレ」のような場面が、実はそこら中にちりばめられているんです。
③「どうやったらできるかな?」正解のない世界だから育つ「主体性」と「探究心」
マイクラには「これをやりなさい」というミッションが用意されているわけではありません。
だからこそ、何をするかはすべて“自分で決める”必要があります。
最初はただ歩き回っているだけだった子が、
「おうちを作ってみようかな」
「村を見つけたけど、ここに道をつなげたいな」
と、少しずつ目的を自分の中で見つけていく姿は、まさに主体性が芽生えている瞬間です。
しかも、やりたいことを実現しようとすると、必ず「壁」にぶつかります。材料が足りない、敵にやられる、建てたものが思った形にならない…などなど。
でもそこで諦めずに、「どうやったらできるんだろう?」と調べたり、試したり、工夫したりして、前に進もうとする姿勢が自然と育っていきます。
「誰かに教えてもらう前に、自分でまずやってみる」そんな風に動けるようになった子は、マイクラの中で“自分の学び方”を見つけたのかもしれません。
大人にとっては見えづらいかもしれませんが、この“自分で課題を見つけて、自分で答えを探そうとする姿勢”は、学校や将来の社会でもとても大事な力です。
マイクラのように正解が決まっていない環境だからこそ、「考える → 試す →工夫する」というサイクルが、自然と回り始めるのだと思います。
④一緒に遊ぶ中で自然と身につく「伝える力」と「協力する力」
マイクラには「マルチプレイ」と呼ばれる、他の人と一緒に同じワールドで遊べる機能があります。
友だちやきょうだいと一緒に遊ぶことで、「協力して何かをつくる」楽しさに目覚める子は少なくありません。
たとえば、
「ここはぼくが建てるから、そっちはお願いね」
「材料が足りないから、一緒に取りに行こう」
「こういう形にしたいんだけど、どう思う?」
こういったやり取りをしているうちに、自然と“伝え方”や“聞く姿勢”が育っていきます。
それに、チームで何かを進めると、思い通りにいかないことも出てきます。「勝手に壊された」「思った通りに作ってくれなかった」なんて小さなトラブルが起こることも。
でも実は、こういう経験がすごく大事なんです。
自分の気持ちを言葉にしたり、相手の立場を考えたり、ちょっとずつ“コミュニケーション”を学んでいくきっかけになります。
言葉にして伝える力、相手と一緒に進める力。マイクラは、そんな“人と一緒に何かをやり遂げる経験”を積む舞台として、とてもよくできた環境なんです。
⑤「できた!」が自信になる。マイクラが育てる「自己肯定感」
最初はただの空き地だった場所に、自分で考えた建物が立ち上がる。「やってみたら、ほんとにできた!」という瞬間のあの顔、見たことありませんか?
マイクラの魅力のひとつは、「自分の手で何かを成し遂げた」という実感が得られるところです。しかもそれを誰かに見せて、「すごいね!」と褒められたら子どもの表情は一気にパッと明るくなります。
完成までに時間がかかったり、途中でやり直しが必要だったりするからこそ、最後に完成したときの達成感はひとしお。それがそのまま、「自分はやればできるんだ」という小さな自信につながっていくんです。
たとえゲームの中であっても、自分で考えたものを形にして、人に見せて、認められるという経験は、子どもにとっては何よりのご褒美です。
この繰り返しが、「自分には得意なことがある」「自分のやったことには意味がある」という自己肯定感を、少しずつ育ててくれます。
そしてその自信は、やがてゲームの外でも、「やってみよう」「チャレンジしてみよう」という一歩につながっていくのです。
マイクラを“学びの時間”にするコツ
マイクラが「教育に良い」と言われる理由はたくさんありますが、実は、どう遊ぶかによってその効果は大きく変わってきます。
ただ画面に向かって夢中になるだけでは、せっかくの可能性がもったいない。でも、だからといって難しいことをしなくても大丈夫です。
ここでは、親子でのちょっとした関わりや、ゆるやかな工夫を通じて、マイクラの時間をもっと“意味ある時間”にする方法をお伝えします。
親子で一緒にプレイする
「マイクラって何が面白いの?」「そんなに夢中になる理由がわからない…」
そんなふうに感じている親御さんこそ、一度お子さんと一緒にプレイしてみてほしいんです。
最初はわからないことだらけでも大丈夫。
「どこに家建てる?」「これ何に使うの?」って子どもに聞いてみるだけでも、嬉しそうに説明してくれるはずです。
その時間そのものが、親子のコミュニケーションになっていきます。
また、一緒にブロックを積んで家を建てたり、村を作ってみたりする中で「これいいね!」って言ってもらえることで、子どもは自分の発想や工夫を“認めてもらえた”と感じて自信がつくんです。
親が一緒に楽しむことで、子どもはマイクラの時間を「ただのゲーム」ではなく、**誰かと一緒に何かを作る“学びの場”**として受け止めるようになっていきます。
「今日はここまで」を決める。それだけで遊びが学びに変わる
マイクラの世界には、終わりがありません。だからこそ、気づいたら何時間もプレイしていた…なんてこともよくありますよね。
でも、だからといって「時間制限!」とピシャリと線を引くだけでは、逆に反発されてしまうことも。
大事なのは、“やめ時”を一方的に決めるのではなく、「今日はここまでにしようか」と一緒に話し合って決めることです。
「次はここを仕上げたい」「ここまでできたら今日は終わりにする」など、ゴールを一緒に設定するだけで、子どもの集中力や計画性がグッと育ちます。
また、「今日はどこまで作れた?」「そのあとどうする予定なの?」と声をかけてみると、自然と振り返りの時間が生まれます。これは立派な“学びの整理”のプロセス。
ルールはガチガチじゃなくて大丈夫。“気持ちよく区切る習慣”があるだけで、遊びの時間が一段と価値あるものになります。
「それ、マイクラでやってみたら?」って言いたくなる活用アイデア
マイクラって、遊び方が自由すぎて、逆に「何をさせたらいいのかわからない…」と悩むこともありますよね。
でも、実は日常のちょっとした会話や宿題からでも、学びのタネは簡単に見つかります。
たとえば、夏休みの自由研究。
「昔のお城を調べたい」→「じゃあマイクラで再現してみようか」
「未来の街ってどうなると思う?」→「マイクラで作ってみたら?」
たったこれだけで、調べて・考えて・作るという立派な学習プロセスが動き出します。
ほかにも、社会や歴史の授業で出てきた建物をマイクラで再現したり、地理の勉強ついでに「日本地図をマイクラで再現してみよう!」なんてアイデアも。
大人がちょっとヒントを出すだけで、子どもたちは自分でどんどん膨らませていきます。
「やってみる?」のひと言が、遊びから学びへのスイッチになるかもしれません。
マイクラで広がる、プログラミングの世界
「マインクラフトで遊んでいたと思ったら、突然“自動ドアを作った!”なんて言い出してびっくりした」
「“この回路をつなげたら動いた!”と、得意げに説明してくれるけど……それってどういうこと?」
そんなふうに、お子さんの“遊びの中のひらめき”に驚いた経験はありませんか?
実はマイクラには、プログラミングの考え方につながる要素がたくさん詰まっています。
レッドストーン回路やコマンドブロックなどを通して、「こうしたら、こう動く」という“論理的な仕組み”を自然と体験しているのです。
だからこそ、お子さんが「もっと仕組みを知りたい」「自分でも動かしてみたい」と感じたその瞬間が、プログラミング学習のベストな入り口になります。
「興味の芽が出てきた今こそ、伸ばすチャンスかもしれない」そんなふうに感じたときには、ぜひ次のステップをのぞいてみてください。
遊びながら“コードのしくみ”が体感できる
マインクラフトでは、ただブロックを積むだけでなく、「動く仕組み」を自分でつくることもできます。
たとえば、スイッチを押すとドアが開く「レッドストーン回路」や、条件を設定して動きを制御できる「コマンドブロック」など。
これらはまさに、プログラミングに必要な“論理的思考”そのものなんです。
「ボタンを押すとどう動く?」「どんな順番で命令を出せばうまくいく?」
遊びながら、子どもたちは自然と“プログラミングコードの流れ”を体感し、試行錯誤を繰り返します。
さらに、教材を使えばその学びは加速します。
命令をブロックのように組み合わせるビジュアルプログラミングから始めて、少しずつ「条件分岐」「繰り返し」などの仕組みも理解できるようになるでしょう。
マイクラを活用したビジュアルプログラミング教材「マイクラッチ」
「うちの子、マイクラは夢中でやるけど、勉強となると腰が重くて…」
そんなご家庭にぴったりなのが、マイクラの世界で“遊ぶように学べる”プログラミング教材「マイクラッチ」です。
「マイクラッチ」は、マインクラフトとScratch(スクラッチ)を組み合わせた、デジタネ独自の教材。
子どもが自分の手でブロックを組み合わせて、建物を出現させたり、キャラクターを動かしたりといった“しかけ”を作れるようになります。
しかも、操作はすべて日本語のブロック式。英語やコード入力は不要なので、タイピングがまだ苦手なお子さんでも大丈夫です。
授業はユーチューバー風の先生「マイクラキング」と「マイクラキャプテン」が楽しくナビゲート。
60個のミッションを、まるでゲームをクリアするような感覚で進められるので、「勉強っぽさ」を感じずに自然とスキルが身につくのが魅力です。
さらに、自分で作ったプログラムは、実際にマイクラ(Java版)上で動かせるので、「自分のプログラムで世界が変わる」というワクワク感が、次のチャレンジへの原動力になります。
『マイクラッチは14日間の無料体験が可能!』
「マイクラッチってどんな教材?」「うちの子に合うかな?」そんな方のために、14日間の無料体験をご用意しています。
まずはお子さまと一緒に、“学びながら遊ぶ”新しいマイクラの楽しみ方を体験してみませんか?
まとめ|「遊び」が「学び」に変わる瞬間を、一緒に見届けてみませんか?
マイクラが「教育に良い」と言われる理由は、ただ知識を詰め込むのではなく、子どもが自分の頭で考え、手を動かし、夢中になれるから。
自由な世界の中で「どうやったらできるかな?」と試行錯誤するその姿は、まさに“学びの原点”そのものです。
そして、マイクラに「プログラミング」という視点を加えると、そこにはまた違った可能性が広がっていきます。
もし、お子さんがマイクラを楽しんでいるなら、それを“学びの時間”に変えてみるチャンスかもしれません。

デジタネ編集部は、小学生〜中高生のお子さまを持つ保護者の方々に向けて、「最新の教育情報」や「学びの悩みを解決するヒント」をわかりやすくお届けしています。
「デジタル教育をより身近にし、未来を担う人材を育む」をミッションとして、日々コンテンツを制作。
社内の専門チームとして、プログラミング教育をはじめ、教育全般やマインクラフト・ロブロックスを活用した学習方法、さらにはタイピングなど基礎的なITスキルまで幅広く発信しています。