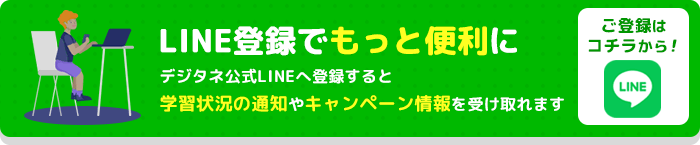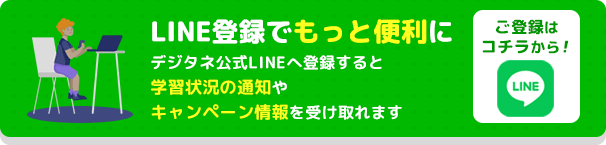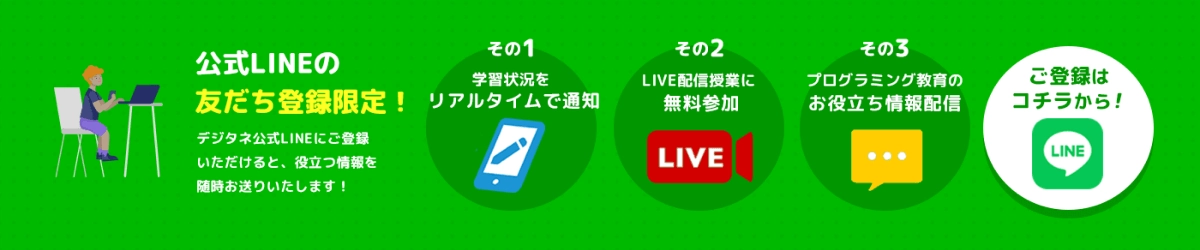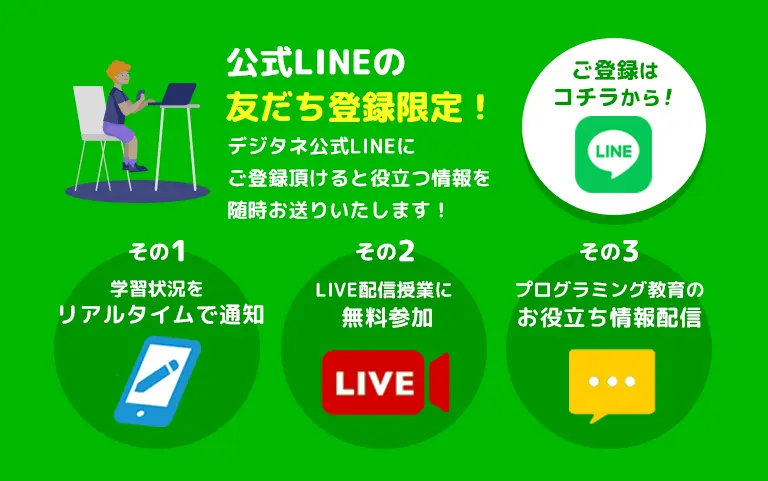「うちの子、気づいたらまたマイクラ…」
そう感じたこと、ありませんか?
最近、子どもたちの間で圧倒的な人気を誇るゲーム『マインクラフト(通称マイクラ)』。
でも親としては、「ずっとゲームばかりで大丈夫?」「勉強がおろそかになるのでは…」と不安になる気持ち、よくわかります。
しかし実は、マイクラは今、教育現場や世界中の先生たちからも“学びの宝庫”として注目されているのをご存じですか?
「ただのゲーム」だと思っていたら…実はそこに、子どもの“非認知能力”や“考える力”を育てるヒントが詰まっていたのです。
今回は、「マイクラばかりしてて心配…」という親御さんに向けて
・なぜマイクラが教育的に注目されているのか?
・マイクラで育つ“5つの力”とは?
・遊びを学びに変える、具体的な方法とは?
をわかりやすく解説していきます。
「心配」を「可能性」に変えるヒントが、きっと見つかるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

マイクラで学べる!小中学生向けオンラインプログラミング教材「デジタネ」。
キャラクター講師がゲーム実況のように楽しく解説してくれるから、マイクラ好きの子どもは勉強感ゼロで楽しく学習!
まずは無料体験で、お子さまにピッタリかどうか試してみましょう!
- 1. 「マイクラばかりで大丈夫?」と感じている親御さんへ
- ・つい言いたくなる「またマイクラ!?」
- ・ゲーム依存や学力低下を心配していませんか?
- 2. そもそもマイクラってどんなゲーム?
- ・ただの「ゲーム」じゃない!子どもが夢中になる理由
- ・“戦うゲーム”ではなく“創る遊び”だからこそ伸びる子どもの力
- 3. マイクラで“頭が良くなる”?育つ5つの力とは?
- ・論理的思考力
- ・空間認識・創造力
- ・問題解決能力
- ・集中力・やり抜く力(Grit)
- ・コミュニケーション・協働性(マルチプレイで)
- 4. その学び、もっと活かせる!“マイクラ×プログラミング教材”という選択肢
- ・プログラミングと組み合わせると「学びが深化」する
- ・楽しいまま“教育”にシフトできる教材は「デジタネ」!
「マイクラばかりで大丈夫?」と感じている親御さんへ
「“学びの宝庫”って言われても、本当にうちの子にとってプラスになってるの…?」
そう感じる方もいるかもしれません。
実際、親として日々の様子を見ていると、
「気づけばまたマイクラ…」「勉強もせずにずっとゲーム…」と、つい不安やイライラが募ってしまうこともあるでしょう。
でもそれって、決してあなただけではありません。
ここではまず、なぜ私たち親が“マイクラばかり”にモヤモヤしてしまうのかを整理しながら、その不安がどこから来ていて、どう向き合っていけばいいのかを一緒に考えていきましょう。
つい言いたくなる「またマイクラ!?」
「えっ、またマイクラやってるの?」「もうちょっと他のこともしようよ…」
そんな言葉が、思わず口から出てしまったことはありませんか?
子どもにとってマイクラは、放っておくと何時間でも没頭してしまうほど魅力的な遊び。
でもその様子を見ていると、「うちの子、このままで大丈夫かな…?」と不安になるのが親心ですよね。
特に、
・宿題より先にマイクラ
・休日は朝から晩までマイクラ
・会話もマイクラの話ばかり
…こんな状態が続くと、つい「やりすぎでは?」「他のことに興味がなくなるのでは?」と心配になってしまいます。
実際、マイクラは自由度が高く、終わりがないゲーム。だからこそ、“どこで区切るか”が見えづらく、親のストレスになりやすいという特徴もあります。
でも、それは「マイクラが悪いから」ではなく、子どもが夢中になれるだけの面白さと可能性を持っているからこそ。
その“夢中”の中にこそ、実は学びの種がたくさん隠れているのです。
次の章では、そんな親の不安の正体と、マイクラとの向き合い方について、もう少し掘り下げてみましょう。
ゲーム依存や学力低下を心配していませんか?
「マイクラに夢中になるのはいいけれど、このままゲームばかりで本当に大丈夫なの…?」
そんなふうに、“ゲーム依存”や“学力の低下”を心配している親御さんは少なくありません。
確かに、何時間も画面を見続けたり、他のことに関心を持たなくなってしまったりすると、不安になるのは当然です。
でも実は、マイクラ=ゲーム依存になる、という単純な話ではないのです。
✅ 「依存」と「熱中」は違う
「依存」という言葉にはネガティブな印象がありますが、一方で“熱中できるものがある”ことは、子どもにとって大きな才能のひとつでもあります。
マイクラで何かを作り上げようと夢中になっている子は、その中で「計画」「試行錯誤」「改善」を繰り返しています。
これって実は、大人の世界でいう“プロジェクト型学習”と同じ構造なんです。
✅ 学力=テストの点数だけでは測れない
「ゲームに夢中で勉強が手につかないのでは?」という声もよく聞きます。
でも今の教育では、いわゆる“テスト力”以外の力(非認知能力)が重視されつつあることをご存じでしょうか?
・自分で考える力
・粘り強さ・やり抜く力
・他人と協力する力
・創造する力
これらは、これからの社会を生き抜くうえで欠かせない力。
そして実はマイクラの中には、こうした力を育む場面が驚くほどたくさんあるのです。
このように、「ゲーム=悪」と決めつけるのではなく、どう活かすか、どう付き合うかでまったく違った価値が生まれます。
次の章では、そもそも「マイクラってどんなゲームなのか?」を改めて確認しながら、その奥に隠れた“学びの可能性”を見ていきましょう。
そもそもマイクラってどんなゲーム?
マイクラは、ブロックでできた3Dの世界を自由に探検し、建築したり、ものづくりを楽しんだりする「サンドボックス型」と呼ばれるゲームです。
特定のストーリーやゴールがなく、プレイヤーが自分で目的を決め、自由に遊び方を組み立てていくのが特徴です。
子どもたちはこの中で、家や町を作ったり、動物を育てたり、時には複雑な仕組みや機械を作ったりすることもできます。
また、ブロックを組み合わせてプログラミング的な動きを作る機能もあり、世界中の教育機関では創造力・論理的思考・問題解決力を養うツールとして活用されています。
マイクラは単なるゲームではなく、子どもたちが“考えて行動する”体験を通じて、楽しみながら学べる環境とも言えるのです。
ただの「ゲーム」じゃない!子どもが夢中になる理由
マイクラの最大の特徴は、「自分で世界を作れること」。
家を建てる、動物を飼う、農場をつくる、洞窟を探検する──やりたいことを自分で決めて、自分のペースで挑戦できる。
その“自由度の高さ”こそが、子どもたちが夢中になる理由のひとつです。
さらに、マイクラの中には「正解」がありません。
自分で考え、失敗し、試行錯誤しながら理想のかたちに近づけていくというプロセスが、子どもたちにとって“遊び”でありながら“挑戦”であり、“学び”にもつながっているのです。
また、設計や仕組みづくりが好きな子は、回路(レッドストーン)やコマンドなどにも興味を持ち始めます。
こうした高度な仕組みを使うことで、論理的思考や創造力が自然と育まれるのもマイクラの魅力です。
加えて、友達や兄弟と同じワールドで協力してプレイすることもでき、コミュニケーションやチームワークを学ぶ場にもなります。
つまりマイクラは、「自由に挑戦し、創造し、学べる」要素が詰まった、単なるゲームとは一線を画す体験型コンテンツなのです。
“戦うゲーム”ではなく“創る遊び”だからこそ伸びる子どもの力
マイクラと聞くと、「敵と戦うゲーム?」「モンスターが出てくるの?」といったイメージを持たれる方もいるかもしれません。
たしかに、そうした“冒険・戦闘”を楽しめるモードもありますが、マイクラの本質はそこではありません。
マイクラの本質であり、子どもたちが最も惹かれているのは“創る”という体験そのものです。
素材を集めて建物を建てたり、村を作ったり、オリジナルの街を設計したりといった「ゼロから何かを形にする」体験が、子どもの想像力や空間認識力、そして粘り強さを育てます。
また、何かを創る過程で「失敗しても壊して何度もやり直せる」「思いついたことをすぐに試せる」といった柔軟さが、子どもたちにとっては“自由な学び”の場になっているのです。
さらに、「どうすれば効率よく作れるか」「もっとかっこよくするにはどうするか」と考える中で、自然と論理的思考や問題解決力も身についていきます。
マイクラで“頭が良くなる”?育つ5つの力とは?
単なる遊びでは終わらない、“創造的に考え、工夫する力”を育むことがマイクラのもうひとつの魅力なのです。
「こんなに夢中になって、何か得るものはあるのかな…?」
マイクラに熱中するお子さんを見て、そんなふうに感じたことはありませんか?
でも実はその“夢中”の中に、子どもたちの力を伸ばすチャンスがたくさん隠れているのです。
ブロックを組み合わせて建物をつくったり、失敗をくり返しながら仕組みを整えたり、こうした体験の中で、考える・工夫する・やりきるといった力が自然と身についていきます。
この章では、マイクラを通して育つ「5つの力」に注目し、
どうして“遊び”が“学び”につながるのか?をわかりやすくご紹介します。
論理的思考力
マイクラの世界では、「何かを作るためには、どの素材が必要で、どんな手順で組み立てるか」を自分で考える必要があります。
この一連の流れこそが、まさに論理的思考のトレーニングです。
例えば、ただ家を建てるだけでも、
1.まずは木を切って、木材に加工する
2.そこから床や壁をどう配置するか考える
3.屋根の形や、窓の位置など細かい構造にも気を配る
といった具合に、「目的」→「材料」→「手順」→「改善」という思考を繰り返します。
さらに高度になると、“レッドストーン”という回路パーツを使った仕組み作りにも挑戦する子どもが出てきます。
これはいわば「プログラミング的思考」の入り口。
順序立てて考える力や、原因と結果を結びつける力が、遊びながら自然と身についていきます。
このように、「言われたことをやる」だけの受け身の勉強とは違い、自分の頭で考えて、手を動かし、試す。そんな主体的な学びの中で、子どもの論理的思考力はどんどん育っていくのです。
空間認識・創造力
マイクラの世界は、すべてが「ブロック」で構成されています。
そのため、建物や構造物をつくるには、立体的な空間を頭の中でイメージしながら形にしていく力が必要になります。
たとえば「2階建ての家をつくろう」と思ったら、
1.どのくらいの高さにする?
2.階段はどこに配置する?
3.上から見たとき、どんな形になる?
といったことを、自然と“図形的・空間的”に考えるようになるのです。
また、マイクラは設計図があるわけではなく、すべてが自由。
だからこそ、「どうしたらもっとかっこよくなるかな?」「水路を引いたら面白そう!」など、発想力や創造力がどんどん引き出される環境になっています。
この「試してみる→失敗する→工夫して完成させる」というサイクルこそが、学校の授業ではなかなか得られない、“自分の頭で考えて創り出す”力を育ててくれるのです。
問題解決能力
マイクラでは、自分で決めた目標を達成するために、以下のようなたくさんの「小さな壁」にぶつかることがあります。
・思ったように建物が完成しない
・モンスターにやられて材料を失ってしまった
・作りたい装置がうまく動かない
こうしたトラブルに対して、子どもたちは「どうしたら解決できるか?」を自分で考え、試行錯誤を重ねるようになります。
マイクラは、正解がひとつではないゲーム。
だからこそ、「このやり方がダメなら、別の方法を試してみよう」といった柔軟な発想力や粘り強さも自然と育ちます。
さらに、オンラインで友達と一緒にプレイする場面では、「役割分担をどうするか」「困っている仲間にどう協力するか」など、周囲との関係を考えながら問題を解く力も求められます。
このように、マイクラの中では“問題が起こること”が当たり前。だからこそ、自分で考え、解決する経験の積み重ねが、大きな学びにつながるのです。
集中力・やり抜く力(Grit)
「気づいたら何時間もマイクラに没頭していた…」
これは一見、ゲーム依存のようにも見えますが、
見方を変えれば、子どもが自発的に集中し続けられる“数少ない環境”とも言えます。
マイクラでは、何かを完成させるまでに時間も手間もかかります。
材料集めから設計、試作、修正まで、そのプロセスはまさに“小さなプロジェクト”の積み重ね。
その中で子どもたちは、
・うまくいかなくても投げ出さずにもう一度やってみる
・「あと少しで完成だから」と集中を保つ
・納得のいくまでこだわって作り上げる
といった経験を、楽しみながら繰り返しています。
これはまさに、近年注目されている非認知能力のひとつ「Grit(やり抜く力)」の育成に直結するものです。
コミュニケーション・協働性(マルチプレイで)
マイクラは1人で遊ぶだけでなく、友達やきょうだいと一緒に同じワールドでプレイできる「マルチプレイ」機能があります。
この中で子どもたちは、「材料を集めておいて!」と声をかけたり、役割分担をしながら一緒に建築したり、困ったときに助け合ったりといったやり取りを通して、自然にコミュニケーション力や協働性を育んでいきます。
また、自分の考えを伝えたり、相手の意見を聞いたりする中で、思いやりや伝える力、チームで物事を進める力も育っていきます。
ただ遊んでいるように見える時間が、実は「人と関わる力」を育てる学びの場にもなっているのです。
その学び、もっと活かせる!“マイクラ×プログラミング教材”という選択肢
ここまでご紹介してきたように、マイクラには創造力や論理的思考、問題解決力など、さまざまな「学びの種」が詰まっています。
でも、せっかくマイクラに熱中しているのなら、“遊び”で終わらせるのではなく、もっと深く・もっと確かな「学び」へとつなげてあげたいと思いませんか?
実は今、マイクラの世界観をそのまま活かして、子どもたちがプログラミングを楽しく学べる教材が増えてきています。
この章では、「マイクラ好きな子にぴったりな学び方」として注目されている“マイクラ×プログラミング教材”の可能性をわかりやすくご紹介します。
プログラミングと組み合わせると「学びが深化」する
マイクラの世界に“プログラミング”を組み合わせると、子どもの学びは一気に深まります。
たとえば、キャラクターを動かすコマンドを自分で入力したり、自動で動く仕掛けをプログラムで作ってみたり、「こうしたい!」という思いを論理的に組み立て、形にしていく力が求められるようになります。
このとき子どもは、
・目的を明確にする(何を作りたいか)
・手順を考える(どうやって動かすか)
・エラーを修正する(なぜうまくいかないのか)
という、まさにプログラミングの基本的な思考プロセスを、遊びながら体験しているのです。
さらに、作ったものがちゃんと動いたときの喜びは格別。
「もっとこうしてみよう」「他にもできることは?」と、自発的な探究心や学びへの前向きな姿勢がどんどん引き出されていきます。
ただのゲームでは終わらず、“好き”をきっかけに、本格的な学びにつながるのが「マイクラ×プログラミング」の大きな魅力です。
楽しいまま“教育”にシフトできる教材は「デジタネ」!
マイクラが好きな子どもにとって、
「学び」への一歩を踏み出すのにぴったりなのが、デジタネの『マイクラッチコース』です。
マイクラッチとは、マイクラの世界観を活かしながら、Scratchのようにブロックを組み合わせる感覚でプログラミングを学べる、デジタネ独自の教材。
組んだブロックの命令がそのままマイクラの世界に反映されるので、“作る→動く→試す”の流れが直感的で、子どもでも楽しみながら理解できます。
さらに、学習はすべて動画形式。親しみやすいユーチューバー風のキャラクターがミッション形式で解説してくれるから、初めての子でもすんなり入れます。
「道を自動で作るプログラム」
「敵キャラが動くミニゲーム」
「空を飛ぶアイテムを自作」
など、自分で“作って遊べる”実感があるから、飽きずに続けられるのもポイントです。
マイクラッチコースは14日間無料で体験することもできるので、マイクラを活用したプログラミング教材に興味がある方はぜひこの機会に⇩からお試しください!
マイクラを“やらせっぱなし”にしない。学びに変える一歩を
マイクラに夢中な子どもを見て、「ずっとゲームばかりで大丈夫かな…」と感じることは少なくありません。
でも、その遊びの中には、創造力・論理的思考・やり抜く力・協働性など、これからの時代に求められる多くの力が育つ可能性があるのです。
大切なのは、「ゲーム=悪い」と決めつけるのではなく、子どもの“好き”をどう学びにつなげていくかという視点。
マイクラをただの娯楽で終わらせず、「学びのきっかけ」に変えてあげることができれば、それはきっと、子どもにとっても親にとっても大きな意味のある体験になります。
今ある“熱中”を、次の成長につなげるために。マイクラは、遊びと学びのちょうど真ん中にあるコンテンツなのかもしれません。

デジタネ編集部は、小学生〜中高生のお子さまを持つ保護者の方々に向けて、「最新の教育情報」や「学びの悩みを解決するヒント」をわかりやすくお届けしています。
「デジタル教育をより身近にし、未来を担う人材を育む」をミッションとして、日々コンテンツを制作。
社内の専門チームとして、プログラミング教育をはじめ、教育全般やマインクラフト・ロブロックスを活用した学習方法、さらにはタイピングなど基礎的なITスキルまで幅広く発信しています。