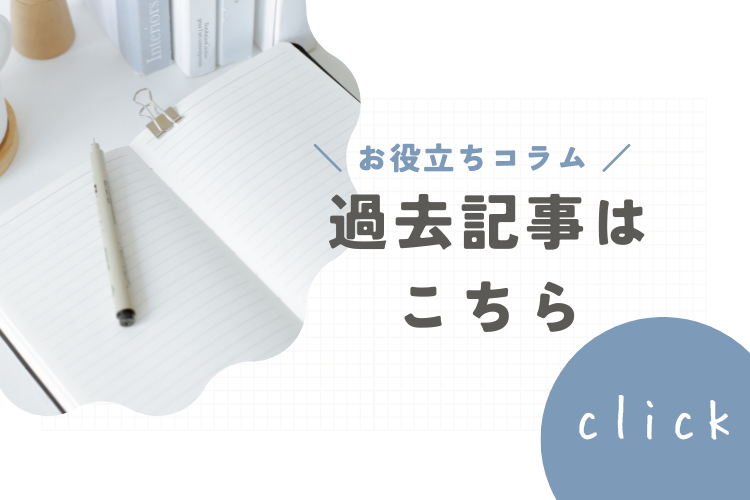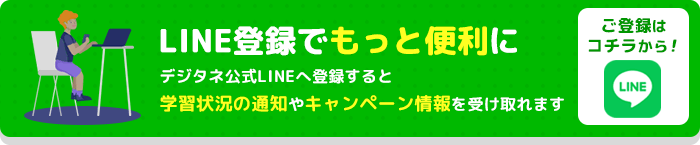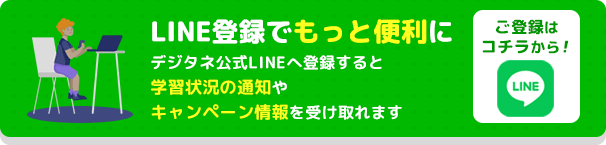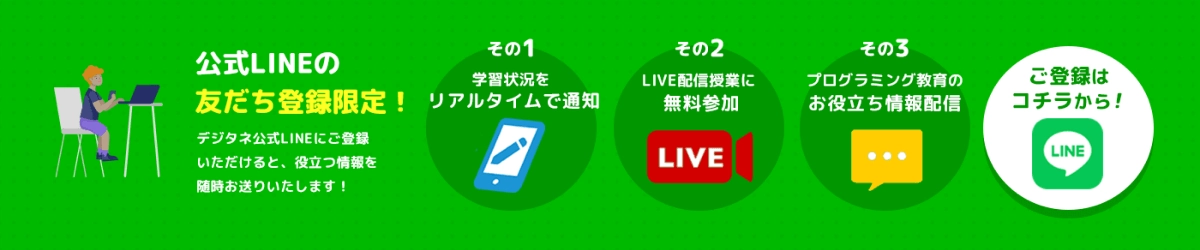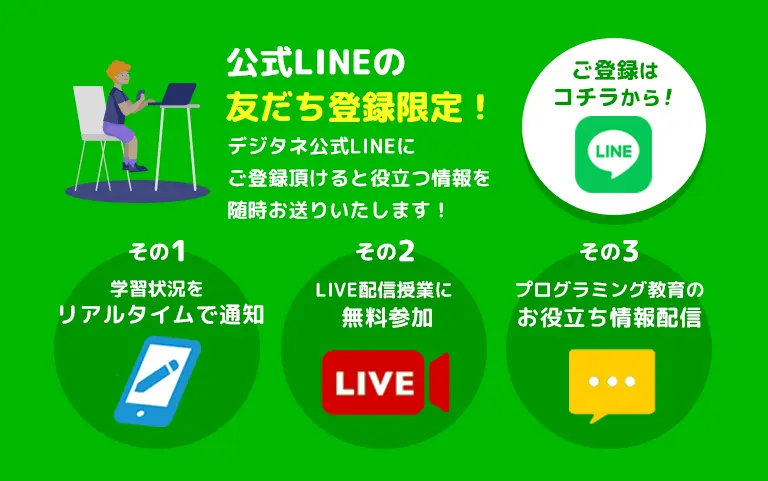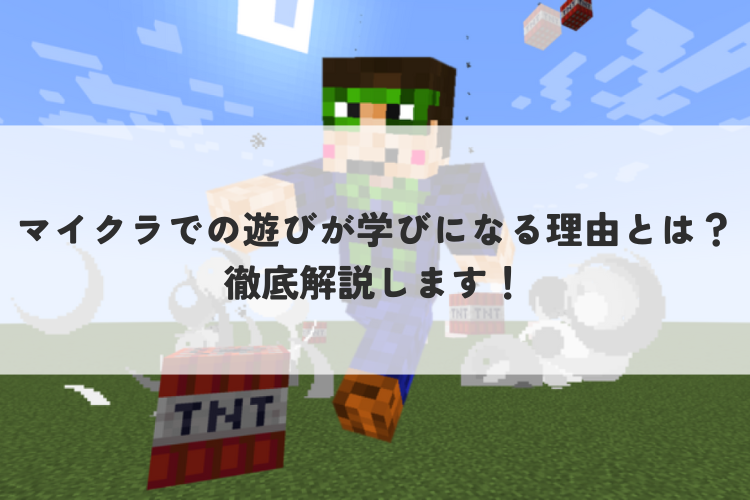
突然ですが、「マインクラフトで頭が良くなる」という言葉を聞いたことがありますか?
あるいは、そんなイメージはありますか?
マインクラフト(以下、マイクラと略)をプレイしているお子さまの中には、一度ハマると延々と遊び続けてしまっているお子さまもいるのではないでしょうか。
そんな姿を見ると「このままで大丈夫か?」と心配になる方も多いはず。
今回はその真相についてお話しします!
ぜひ最後までお読みください。
そもそもマインクラフトって?

引用:マイクラ公式ページ
マイクラとは、3Dのブロックだけでできた世界の中で、ブロックやアイテムを用いて建物や風景を作ったり、モンスターと戦ったり、冒険をしたり…とにかく何でもできるゲームです。
見た目はとてもシンプルですが、実は非常に奥が深いのがマイクラの特徴です。
「建物建築のシーン」を例にしてみましょう。マイクラで建物を作るためには以下の手順が必要です。
1.建物を作るための「設計を思い描く・作る」
2.数あるブロックの中から「適切なブロックを選ぶ」
3.ブロックを「正しく設置する」

上記の「建築」はあくまでマイクラ遊びの中の「一要素」であり、他にも数えきれないほどの遊び方があるので、かなり奥が深いゲームといえるでしょう。
また、以下の記事ではマイクラの特徴について細かく解説しているので、ぜひご一読ください。
【💡マイクラってどんなゲーム?】
マイクラってどんなゲーム?子どものプログラミング学習に効果ある?【マイクラキング解説】
マインクラフト=頭が良くなるというのは本当?
結論、「マインクラフトを遊ぶことが直接頭を良くする」と断言することはできません。
しかし、「将来役に立つスキルが身につく」ことは期待できると言っていいでしょう。
実際に、マイクラが教育的に効果があることから、多くの日本・海外の教育現場でマイクラが活用されています。
以下で事例をみてみましょう。
【日本の教育現場での活用事例】
京都にある「立命館小学校」では、5・6年生を対象に「マインクラフト教育版」を使った授業が行われています。
授業内容は、社会科の授業で京都の歴史を学びつつ、仮想空間で世界遺産の建物や伝統的建築物を作るというもの。
具体的には下記の3つの手順で授業が行われます。
1.作成する建物を設計図から作成
2.ブロックを積み上げ建造物を制作
3.最終的には海外の学校向けに英語でプレゼンテーションを行う
このような活動から、
・コミュニケーションの活性化
・問題解決能力の向上
・プレゼンテーションスキルの向上
が期待されています。
【海外の教育現場での活用事例】
アメリカ・カリフォルニア州の「Del Mar Middle School」によって「Digging for Truth」という授業が行われています。
内容は、アメリカの狩猟採集時代~帝国発生までの文明の変化・過程を再現し、時代ごとに与えられた以下のような課題をクリアするというもの。
1.火おこしをする
2.簡易的な家をつくる
3.道具をつくる
この授業から、
・文明の変化などを体感し、歴史に対する興味
・同じ課題に取り組むことで、問題解決能力の向上
が養えるとのことです。
参照:https://stonewashersjournal.com/2014/07/17/minecraftonschool/
マインクラフト×プログラミングは相性抜群!
上記はマイクラの中で遊びながら学ぶというものですが、マイクラにプログラミングを組み合わせることにより、ただ遊ぶだけよりもさらに効率的に能力を養うことができます!
例えば、マイクラで建物を建てる場合、通常は設計からブロックの配置までですが、プログラミングを加えると「プログラムを書く」作業が必要になります。
この過程を通じて、子どもたちは遊び感覚でプログラミングを学ぶことができるので、楽しみながら学習に取り組めるんです。
せっかくならプログラミングもいっしょに学んでみませんか?
お子さまがせっかくマイクラにハマっているなら、ぜひマイクラと相性抜群の「プログラミング」も一緒に学んでみてはいかがでしょうか?
小・中学生向けオンラインプログラミング教材の【デジタネ】では、マイクラを活用してプログラミングを学ぶ「マイクラッチコース」をご用意しています。
以下の動画をご覧ください。(※音量注意)
マイクラッチコースは、まるでYouTubeのようにアバターの先生が解説をしているので、楽しくプログラミングを学ぶことができます。
また、ミッションごとに異なるゲームを作っていくので飽きずに続けられます!
現在14日間の無料体験を実施しているので、ぜひこの機会にお試しください。
▼14日間無料体験の登録はこちら!

デジタネ編集部は、小学生〜中高生のお子さまを持つ保護者の方々に向けて、「最新の教育情報」や「学びの悩みを解決するヒント」をわかりやすくお届けしています。
「デジタル教育をより身近にし、未来を担う人材を育む」をミッションとして、日々コンテンツを制作。
社内の専門チームとして、プログラミング教育をはじめ、教育全般やマインクラフト・ロブロックスを活用した学習方法、さらにはタイピングなど基礎的なITスキルまで幅広く発信しています。