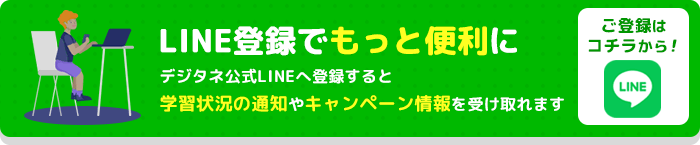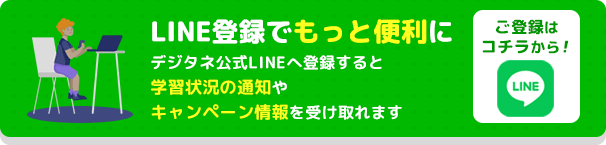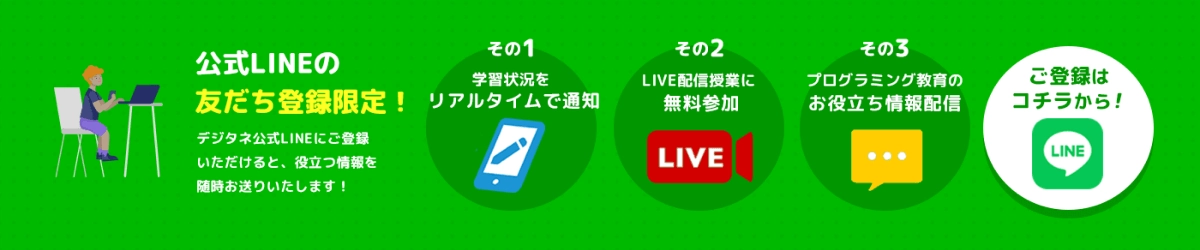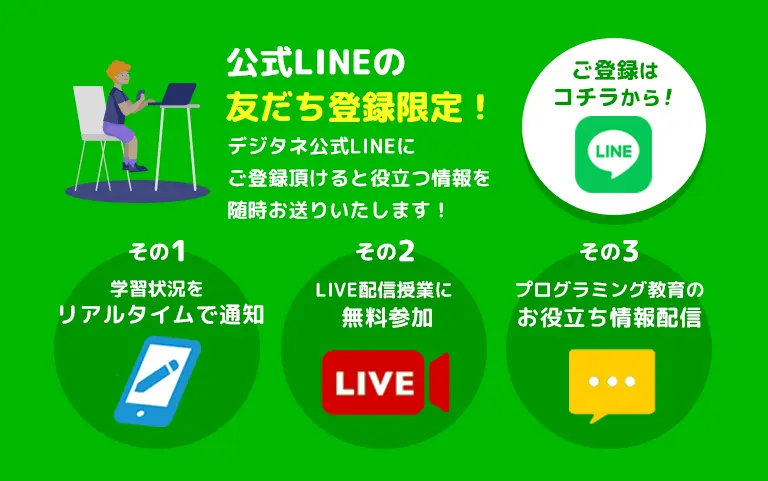最近、「AI(エーアイ)」という言葉をよく聞くようになりました。
ニュースや学校のおたより、子どもたちの会話にも出てくるので、「うちの子にもAI教育って必要なのかな?」と感じている保護者の方は増えています。
「AI教育」とは、AIを“使いこなす力”と“AI時代でも自分で考えられる力”を育てる学びのことです。
そして、AI教育は“特別な子だけの学び”ではありません。
むしろこれからの小学生にとって当たり前の教養になっていくといわれています。
とはいえ、いきなり難しい勉強を始める必要はありませんし、AIの仕組みを深く理解する必要もありません。
大切なのは、「AIとどう上手につきあっていくか」「便利さに流されず、自分の頭で考え続けられるか」という部分です。
この記事では、
・なぜ今、小学生にもAI教育が必要と言われているのか
・AIを学ぶことで子どもにどんな変化が生まれるのか
・家庭では何から始めれば良いのか
この3点を、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。ぜひ参考にしてみてください。
\お子さまのAI教育の一環としてプログラミングを学びませんか?/

AI時代における小学生の学びとは?

今、私たちの身のまわりでは、気づかないうちにAIが使われる場面がどんどん増えています。
動画アプリのおすすめ表示も、写真の自動加工も、子どもが学校で使うタブレット学習も、実はAIの力が使われています。
こうした変化は、子どもたちの“学び方”にも大きな影響を与えています。
「AIをどう使うか」や「AIとどう関わるか」を知っているかどうかで、将来の選択肢が変わってくる時代になりつつあります。
ここでは、学校や家庭で進んでいるAI化の流れを、わかりやすく紹介していきます。
学校のデジタル化・AI化の流れ
結論からお伝えすると、学校の学びはここ数年で大きく変わり、AIを使った授業や教材が増えてきています。
たとえば、多くの小学校では、
・1人1台のタブレット学習
・子どもの理解度に合わせて教材を変える仕組み
などが導入されています。
これは「GIGAスクール構想」と呼ばれる取り組みによって、全国の学校でデジタル化が一気に進んだためです。
こうした動きにより、先生が黒板の前で説明するだけの授業から、子どもが自分で画面を操作しながら学ぶ“参加型の授業” へと変わりつつあります。
もちろん、すべての学校で完璧にAIが使われているわけではありません。
ただ、国全体として「子どもがAIを使いこなせるようになる」ことを目指しており、その流れは今後さらに加速するといわれています。
家庭でも求められる「AIリテラシー」とは何か
AIリテラシーという言葉は少しむずかしく聞こえますが、意味はとてもシンプルです。
AIを便利に使いつつ、自分で考える姿勢を忘れないこと。家庭で求められるのは、まずこの姿勢です。
今の子どもたちは、家庭の中でもさまざまな場面でAIに触れています。
動画の検索結果が自動で表示されたり、写真の明るさが一瞬で調整されたり。大人が気づかないところで、AIの働きがすでに生活の一部になっています。
だからこそ、「AIが言っているから正しい」と思い込まず、“本当にそうかな?” と一度立ち止まって考えられる力 が大切になってきます。
この小さな習慣が、のちのち子どもの判断力や思考力につながっていきます。
たとえば、AIが出した答えが少し違っていたときに一緒に調べてみたり、
子どもがアプリを使う様子を見ながら「どうしてそう思ったの?」と聞いてみたりするだけでも十分です。
特別な教材を使わなくても、家庭にある“ちょっとした会話”の中で育てられる力なのです。
小学生がAI教育を受けることで得られる5つのメリット
小学生のうちからAIに触れることによって、学力そのものよりも“生きる力”のような土台が育つと言われています。
AIを使う場面が増えるほど、子どもたちの思考の幅は広がり、自分で考えて動く力も伸びていきます。
これらは、将来どんな道に進んだとしても役に立つ、なくてはならない力です。
ここからは、小学生のうちにAI教育に触れることで、どんな良い変化が生まれるのかを、5つの視点でわかりやすく紹介していきます。
論理的に考える力・自分で解決する力が身につく
AIに触れる時間が増えると、子どもたちは自然と「考え方の筋道」を意識できるようになります。
これは、いわゆる“論理的思考力”と呼ばれる力で、問題を順番に整理しながら答えを見つけていく力です。
たとえば、AIに質問を投げかけたとき、うまく答えが返ってこないことがあります。
そのとき子どもは、「どう聞けば伝わるかな?」と試行錯誤します。この小さなやりとりこそが、筋道を立てて考える力を育てるのです。
また、AIが出した答えが少し違っていたときに、自分で調べなおしたり、理由を考えたりする場面も出てきます。
こうした経験が積み重なることで、目の前の問題を一つずつ解決していく力が育っていきます。
特別な教材や難しい理論がなくても、AIを使った日常のやりとりの中で、子どもの“考える力”はしっかり伸ばせるのです。
創造力・発想力を養う
AIを使った学びには、子どもが「こんなこともできるんだ!」とワクワクする瞬間がたくさんあります。
そのワクワクが、創造力や発想力を広げるきっかけになります。
たとえば、AIに「こういう絵を描いてほしい」とお願いしたり、アイデアを相談してみたりすると、思いがけない答えが返ってきます。
その答えをヒントに、「じゃあ次はこうしてみよう」と自分なりの工夫を加えるようになります。
AIは“正解”だけを教える存在ではありません。
子どもの頭の中にあるイメージをふくらませたり、まだ知らない表現に出会わせてくれたりする良い相棒です。
新しい刺激が増えるほど、「こうしたい」という気持ちが育ち、ものづくりへの意欲も高まっていきます。
遊びと学びがつながるような感覚で、楽しみながら創造力が育っていくのがAI教育の魅力のひとつです。
“できた!”を通じた自信づくり
AIを使った学びは、子どもが「できた!」と実感しやすいのが大きな特徴です。
難しすぎず、かといって単なる作業ではない“ちょうどいい挑戦”が多いため、小さな成功体験が積み重なります。
AIに描いてほしい絵をうまく伝えられた瞬間や、AIが出したヒントをもとに問題を解けたときなど、「あ、できた!」という喜びが、子ども自身の自信につながっていきます。
そして、この“できた経験”は学びへの意欲を高める力があります。
一度自分の力で結果を出せると、「もう少しやってみたい」「次はこんなこともできるかな」と、自然に前向きな気持ちが生まれるからです。
AI教育の良さは、失敗してもすぐにやり直せるところにもあります。
何度でも試せる環境の中で、小さな成功体験を重ねていくことで、子どもの自己肯定感はゆっくりと、けれど確実に育っていきます。
将来の選択肢を広げる準備として
AIが当たり前に使われる時代では、どんな職業に進んでも「AIとどう関わるか」が避けられません。
だからこそ、小学生のうちからAIに触れておくことが、将来の幅を広げることにつながります。
子どもの興味は成長とともに大きく変わっていきます。
今はスポーツに夢中でも、数年後にはものづくりに興味を持つかもしれませんし、逆に理系が苦手だと思っていても、実はAIを使った分野で力を発揮する可能性もあります。
AIに慣れておけば、将来どの道を選んでもスタートがスムーズになります。
たとえば、デザイン、教育、医療、サービス業など、一見AIと関係がなさそうな仕事でも、AIを活用する場面がどんどん増えています。
「早く始めたから必ず成功する」という話ではありませんが、
AIと自然に関われる経験があるだけで、将来の選択肢は確実に広がります。
それは、子ども自身が「やってみたい」と思ったときに、一歩を踏み出しやすくなることにつながるからです。
親子の会話が増え、家庭学習もスムーズになる
AIを使った学びは、親子のコミュニケーションにも良い影響があります。
子どもがAIに質問したり、試した結果を見せてくれたりすると、自然と「どうしてこうなるの?」という会話が生まれます。
ときにはAIの答えがズレることもあり、その“ちょっとした違い”が「一緒に調べてみようか」と声をかけるきっかけになります。
こうした小さなやり取りが積み重なると、家庭学習の雰囲気がやわらかくなり、子どもも前向きに取り組みやすくなります。
また、子どもがAIで作った絵や文章を見て「おもしろいね」と声をかけるだけでも、学びへの意欲がぐっと高まります。
AI教育はスキルだけでなく、親子で学びを共有できる“コミュニケーションのきっかけ”にもなるのです。
小学生がAIを活用する際に知っておきたい注意点・課題も
AIはとても便利で、学びの幅も広げてくれますが、使い方によっては気をつけたい点もあります。
といっても、特別な対策が必要というわけではありません。
保護者がいくつかのポイントを知っておくだけで、安心して子どもにAIを使わせることができます。
ここでは、日常の中でも意識しておきたい「AIとの付き合い方」について、無理なくできる内容にしぼって紹介していきます。
AIに頼りすぎない
AIは便利ですが、なんでも自動でやってくれるわけではありません。
ときには間違った答えを出すこともあり、そのまま受け取ってしまうと勘違いにつながることもあります。
だからこそ、AIを使うときは「本当にそうかな?」と一度立ち止まる習慣が大切になります。
子どもは、AIがすぐに答えを出してくれると、それだけで満足してしまうことがあります。
しかし、その答えをもとに自分なりの考えを足していくことで、学びが深まっていきます。
親がそっと声をかけてあげるだけでも、「自分で考えてみる」という姿勢が自然と身くでしょう。
環境によって、AIの学びやすさが変わることもある
AIを使った学びには良い面が多い一方で、どんな環境で使うかによって“取り組みやすさ”が変わることがあります。
たとえば、タブレットの動きが遅かったり、ネットが不安定だと、子どもが思ったように操作できず、学びが進みにくいことがあります。
また、AIの使い方をサポートしてくれる大人が近くにいるだけで、子どもは安心して挑戦できます。
困ったときに気軽に質問できたり、ちょっとした使い方を教えてもらえたりするだけで、取り組み方が大きく変わるからです。
完璧な環境を整える必要はありません。
ただ、「スムーズに使えるかどうか」「わからないときに聞ける人がいるかどうか」を意識してあげると、子どもはAIをもっと楽しく、前向きに使えるようになります。
子どものプライバシーを守る
AIを使うサービスの中には、名前や写真などの情報が残るものもあります。
基本的には安全に配慮されていますが、どんな情報が扱われているのかを親が知っておくと、より安心して使えます。
たとえば、ログイン名を本名にしない、写真の共有設定をオフにするなど、ちょっとした工夫で安全性は高まります。
また、子どもにも「大事な情報はむやみに書かない」というシンプルなルールを伝えておくだけで十分です。
難しい対策をしなくても、少し気を配るだけでAIを安心して使うことができます。
小学生のAI教育は何から始めたら良いの?
AI教育の入り口は、とてもシンプルです。
まずは子どもが「ちょっとやってみたい」と思える環境をつくることが大切です。
ここでは家庭で無理なく始められる3つのステップを紹介します。
① 身近なAIに気づくことから始める
まずは、ふだんの生活の中にあるAIを親子で一緒に見つけてみましょう。
YouTubeの「おすすめ動画」や、写真アプリの自動補正、スマートスピーカーの返事など、子どもたちの生活にはすでにAIがたくさん使われています。
「これもAIが考えてくれているんだよ」と軽く伝えるだけで、AIが特別な存在ではなく“身近な道具”だと感じてもらえるようになります。
② 子どもでも使えるAIツールに触れてみる
次のステップとして、子どもが楽しめる簡単なAIツールに触れてみるのがおすすめです。
たとえば、絵を作ってくれるアプリにお願いしたり、音声アシスタントに質問してみたりすると、AIの面白さがすぐに伝わります。
最初は「遊び」の延長で構いません。
楽しみながらAIに慣れていくことで、自然と興味が広がり、次の学びへ進みやすくなります。
③ AIの答えを“そのまま信じない”習慣をつくる
AIは便利ですが、間違った答えを出すこともあります。
だからこそ、「本当にそうかな?」と一度考えてみる習慣をつけてあげることが大切です。
親が「どうしてそう思ったの?」「ほかのやり方もあるかな?」と声をかけるだけで、子どもはAIと自分の考えを比べられるようになります。
これが、AI時代に必要な“考える力”の土台になります。
AI教育の一環としてまずはプログラミングから始めてみませんか?

AI教育を始めるといっても、いきなり高度な内容に取り組む必要はありません。
むしろ、小学生にとっては プログラミングが“ちょうどいい入り口” になります。
プログラミングは、AIと関わるうえで欠かせない「考える力」や「筋道を立てる力」を、遊びながら身につけられる学びです。
難しい数式や英語を使わなくても、ブロックを組み合わせるように操作するだけで仕組みがわかってくるため、初めての子どもでも楽しく取り組めます。
ここからは、なぜプログラミングがAI教育につながるのか、そして小学生にぴったりな理由をわかりやすく紹介していきます。
① プログラミングは“AI時代の土台づくり”になる
AIは「入力された情報をどう処理して結果を出すか」という仕組みで動きます。
これはプログラミングの考え方ととても近く、プログラミングを学ぶことでAIの仕組みを理解しやすくなる というメリットがあります。
② 小学生でも無理なく楽しめて、成功体験を積みやすい
今のプログラミング学習は「遊びながら学べる」ものが多く、ゲームをつくったり、キャラクターを動かしたりしながら学ぶことができます。
「できた!」の積み重ねがAI教育で大事な“自信”にもつながるので、
プログラミングはその入口としてちょうどよく、机に向かう勉強が苦手な子でも入りやすいのが特徴です。
③ 家庭で始めやすく、オンライン学習との相性が良い
プログラミングは、タブレットやパソコンがあれば家でもすぐ始められます。
送迎の必要がなく、子どものペースで進められるため、忙しいご家庭でも続けやすい学びです。
特にオンラインのプログラミング教室は、小学生向けに工夫されたレッスンが多く、「AI教育の入口として、まずはプログラミング」というご家庭が増えています。
小学生向けプログラミング教材の『デジタネ』なら、初めての子でも安心して始められる
デジタネは、小学生向けのオンラインプログラミング教材です。
プログラミングが初めてのお子さまでも無理なく取り組めるように、動画を観ながら進められるスタイルになっています。
また、子どもたちに人気のマインクラフトやロブロックスを使って学ぶため、
「遊びながら自然と考える力が身についていく」という声も多く、プログラミングのハードルをぐっと下げてくれます。
AI教育にいきなり取り組むのは難しく感じても、まずは“自分で動かしてみる学び”を重ねることで、AI時代に必要な思考力や発想力が育っていきます。
プログラミングは、その最初の一歩としてとても相性の良い学びです。
デジタネでは14日間の無料体験が用意されているので、「興味はあるけれど続けられるか心配…」というご家庭でも、まずはお子さまとの相性を確認できます。
3ステップで簡単に登録ができるので、ぜひこの機会に⇩以下からおためしください!

デジタネ編集部は、小学生〜中高生のお子さまを持つ保護者の方々に向けて、「最新の教育情報」や「学びの悩みを解決するヒント」をわかりやすくお届けしています。
「デジタル教育をより身近にし、未来を担う人材を育む」をミッションとして、日々コンテンツを制作。
社内の専門チームとして、プログラミング教育をはじめ、教育全般やマインクラフト・ロブロックスを活用した学習方法、さらにはタイピングなど基礎的なITスキルまで幅広く発信しています。